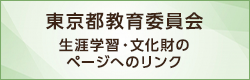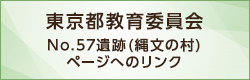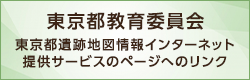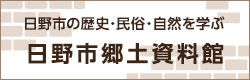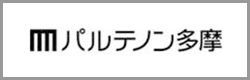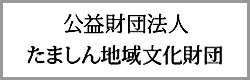東京都埋蔵文化財センター
発掘トピックス詳細情報
原町西遺跡
| よみがな | はらまちにし いせき |
|---|---|
| 発掘場所 | 文京区 白山4丁目 10 番8 |
| 主な時代 | 近世 |
遺跡の特徴
原町西遺跡は文京区中央部に位置する小石川植物園の北側に隣接します。旧町名「原町」の西端部に位置し、北西側は旧町名「林町」に隣接します。標高は、およそ25mです。本調査区周辺では、1980 年に日本専売公社宿舎改築に伴い白山4丁目遺跡(No.46:白山四丁目1225)、1994年に徳島県職員住宅改築に伴い原町遺跡(No.21:白山四丁目612)、1999年に第一勧銀白山アパート跡地の白山御殿町遺跡(No.84:春日一丁目1621)、2002年に東京海上林町住宅跡地の林町遺跡(No.26:千石二丁目11)、2018年に日本銀行原町家族寮跡地の原町遺跡(No.22:白山四丁目718)が調査されたほか、東京大学小石川植物園内で数多くの調査事例が積み重ねられています。
本調査区には、徳川綱吉が将軍時代の1698年(元禄11年)に小石川御殿を拡張した際に構築された 、御殿を取り囲む幅10間(約18m)と言われる堀が位置していたと想定されています。
堀自体は、将軍家継の命により1713年(正徳3年)に埋め戻されました。当調査区は、埋め戻された後に武家屋敷として変遷し、近代には大蔵大臣や東京市長を歴任した阪谷芳郎邸、1950年に最高裁判所の敷地となり現在に至ります。

第1図 一万分の一地形図東京近傍「早稲田」の一部(1925(大正14)年)
赤枠内が阪谷芳郎邸敷地、赤塗りつぶし部分が今回調査対象区である「原町西遺跡」範囲
トピックス
原町西と名付けられた今回の調査区を語る際に、江戸幕府五代将軍徳川綱吉を抜きに語ることはできません。従来は「生類憐みの令」に代表されるような暴君のイメージが定着していましたが、近年は従来の戦国の気風が色濃く残る江戸幕府当初の武力統治から儒学思想に基づく仁愛統治への転換を図ったという見直しの機運が高まっています(朝日新聞2024年10月30日記事など)。そうした綱吉が残した幅18m・深さ5m総延長2kmとされる水堀が、小石川御殿(現在の東京大学小石川植物園)を取り囲んでいました。今回の発掘調査で、その御殿堀の一端が姿を現しました。
絵図などの文献には記されており、以前からその存在は予想されていた御殿堀、それが最初に発掘調査で確認されたのは、今回の調査区から南東に270mほど離れた「徳島県白山職員住宅」を構築するために1994年に行われた発掘調査でした。この時に確認された遺構は、徳川綱吉に由来する御殿堀であると明確には認定されませんでしたが、296年前にその堀を掘削するように綱吉から命じられたのが阿波徳島藩の蜂須賀綱矩であったことも、何か不思議な縁のように思われます。
(2024年11月現在)

写真1:第2区において御殿堀の北東側の法面と底面を検出している状況です。右側に見えている段は、調査区境において安全勾配を維持するために1m単位で形成したもので、地表から堀底面まで4mほどの深さがあることが判ります。法面は地山であるローム層を平滑に削り出していますが、特に粘土を貼り付けたような加工の痕跡は認められませんでした。

写真2:第2区における御殿堀の完掘状況です。左側南西方向から伸びる堀が右側南東方向へ90度直角に折れ曲がる「コーナー部分」が初めて確認されました。 コーナー部分の屈折部には、上下に昇り降りするためのステップが構築されています。屈折部左側に見える切れ込みは、北西方向に続く千川上水の出水口です。